2007年度勉強会の内容
■第一回<波頭亮先生>
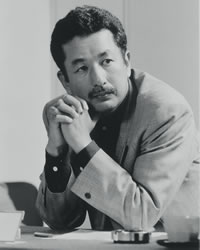
◆概要
メンバー自己紹介、および講師紹介を通じ、LIPという勉強会の意義、この会で学んで欲しいことを波頭先生に語っていただいた。
◆講義内容
<心構え>
・社会人と学生の一般常識のギャップについての説諭。信頼関係と責任の重みについて。
・事物の表層だけを一面的に捉えるのではなく、もっと深部まで多面的に自分自身で考え、検証するくせをつけるべき。鵜呑みは危険(cf. タバコ産業とWHOの関係)。
<メッセージ>
・価値あるものは価値あると素直に認められる人間になってほしい。優秀な人間をつぶす側の人間にだけはなって欲しくない(cf. 中西準子博士)。
勉強会の感想はこちら≫
■第二回<三枝成彰先生>
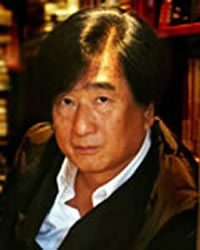
◆概要
自身の信念を曲げず、時代の寵児から一転どん底人生に転落しても10年以上耐え続け、這い上がり、ついにまたオペラ界で世界のトップに返り咲いた三枝先生のすさまじくも力強い人生について語っていただいた。
◆講義内容
<心構え>
・人生自分の好きなことをやっていればどんなにつらい状況でも耐え忍べる。楽しむことができる。
・例え借金を2億、3億と背負おうことになっても、好きなことをやれる満足感があれば吹き飛ばすことができる。
・自分が本当にやりたいことは何か、好きなことは何なのかよく考えるべき。そして好きなことを全力でやるべき。
<メッセージ>
・好きなことをやるためにはお金が必要。そのためなら営業活動でも何で
積極的にやるべき。
・人の輪に積極的に入り、人脈をどんどん広げるべき。
・どんなことにも興味をもち、どんどん顔を突っ込んでいくことが肝心。
・チャンスは多いところには転がっている。生涯アクティブに活動したいなら、日本では断然チャンスの豊富な東京に住むべき。
勉強会の感想はこちら≫
■第三回<北谷賢司先生>

◆概要
興行ビジネス界における日本の顔として長年国際的に活躍されてきた北谷先生に、日本社会、会社組織の体質に対する想いや価値観を語っていただいた。
◆講義内容
<日本的な組織、社会に対する考え方>
・日本社会、会社組織は非常に排他的。
・日本は一個人として組織に溶け込むのが難しい国。
・立ちはだかるバリアーを破る勇気が必要。
・終身雇用で組織を硬直化させることにはもう意味がない。人材をもっと流動的に動かせる仕組みにする必要が高い。
・そのためにもある一定ラインの管理職以上はサラリーマンではなく契約社員の身分にすべき。
<心構え>
・組織の中で動く場合、大切なのはphilosophyをもった意見や意思、philosophyの伴った行動。
・公益に奉仕すること(philanthropy)にもっと日本企業、日本の個人は価値を見出してほしい。
・先生は個人としては「衣食住足りて礼節を知る」で良いという立場。社会貢献は自身の成功のあとでゆっくりやればよい。
勉強会の感想はこちら≫
■第四回<南場智子先生>

◆概要
経営コンサルタント・起業家として日本をリードしてきた南場先生に、ご自分の人生について、DeNAと共に歩んできた道について、そしてそこから得られた経験と思いについて講義していただきました。
◆講義内容
<マッキンゼーから現在にいたるまで>
・「お金を頂くことの重圧」を噛み締めて苦労した最初の数年。
・ふとそこから開放されるMBA取得のための「学生」時代。
・再び始まったマッキンゼーのキャリアと物足りなさ。
・クライアントに拒否されたビジネスモデルで、「魔がさして」起業。
・システム屋にだまされて窮地に陥った「ビッダーズ開業1ヶ月前」。
・周りの助けと努力で達成したDeNAの成長。
・上場は企業の巣立ち、株主が敵になる。
<心構え>
・(南場さんの)サクセスドライバーは「成功への望み」と「責任感」。
・世の中には「報われることを願う幸せ」と「そもそも苦労しない幸せ」がある。
・苦労した後の成功が人を大きく成長させる。
・ロジカルなだけでは見えない光もある。
・起業はトータルな人間力と細かい所をつめる緻密さが重要。
勉強会の感想はこちら≫
■第五回<團紀彦先生>

◆概要
社会の曲がったことには決して屈服せず自身の信念を貫き通されてきた團先生に、ご自身の生き様、価値観を語っていただいた。
◆講義内容
<愛知万博の舞台裏エピソード>
・團先生を含む3名のチームは2005年の万博マスタープランを作成された。初期のプランは自然の野山を最小限しか開発せず、万博終了後は元の自然の野山に戻すというコンセプトだった。このアイデアが決め手となり、万博の愛知での開催が決まった。
・しかし開催決定後、国は利権の分配がしやすい(開発中心の)プランにコンセプトを挿げ替え、しかもその事実は国際社会に開催前年までの2年間ひた隠しにされ続けた。
・團先生はこのことに反発し、建設省を相手に最後まで抗議し続けられた。
・間違っていることは間違っていると声を大に主張することの大切さを語っていただいた。
<価値観>
・日本では「公」の概念が希薄。「官」×「民」=「公」であるはずなのに日本では「官」≒「公」と認識されている。
・日本の町並みがグチャグチャしているのも、通りは「公」のものという「民」の理解が欠如しているため。部分は自立しているが全体としては調和が取れていない。
・「公」というものに対する「民」の理解レベルを引き上げたい。
・團先生はそのために都市の再開発を手がけておられる。ブロックではなく、特に「通り」ごとに統一性をもたせようと、異なる不動産会社間での折衝等に尽力されている。
勉強会の感想はこちら≫ |

