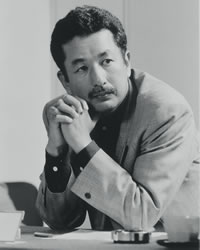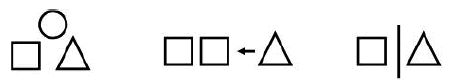2008年度勉強会の内容
■第一回・第二回<波頭亮先生>
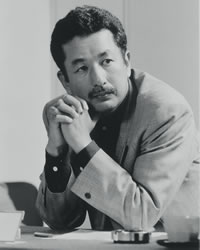
波頭亮先生はMckinsey&Companyをご卒業後、ご自身の会社(株)XEEDを立ち上げられ、現在日本でもっとも注目される戦略コンサルタントの一人としてご活躍されています。また独自の視点からの経済論評や、リーダーシップ、プロフェッショナリズムに関する著書を出版するなど、そのご活躍は多岐に渡ります。本会はそもそも波頭先生のご発案で昨年度立ち上がった勉強会であり、会全体を通して先生にはオーガナイザーとして献身的に学生たちへの啓蒙、啓発をしていただきました。

■第三回<西川伸一先生>

西川伸一先生は近年iPS細胞の発見で世界的注目を集めた京都大学の山中伸弥教授の師にあたる方で、山中教授をはじめ、多数の優秀な研究者を日本から世界に輩出されてきました。ご自身も再生医学、特に幹細胞の研究で世界的な権威でいらっしゃるのみならず、日本の医療、医学界に対して医局の外から建設的な提言を多数されており、志、言、動に筋の通ったすばらしい方です。今回LIP2008の勉強会では「イデオロギーとしての生物学」というテーマでご講演いただきました。iPS細胞の発見により人類は(倫理問題抜きで)原理的には自分の臓器を複製したり、治療したり、将来的には無性生殖さえも可能にする手段を手にしてしまいました。生命体として根幹的な死生観そのものを大きく覆しかねないiPS細胞の出現などにより、21世紀初頭に再びイデオロギーの時代が到来するかもしれません。西川先生は一科学者の立場から、来るべきパラダイムシフトに対して生命科学から生まれた事実を基礎として新しい世界観、新しい文化のあり方を構築できないかとお考えです。
上記の観点から先生は本当に様々なお話をわかりやすく、スライドを交えながら説明してくださりました。DNAと言語(チョムスキー生成文法の普遍文法の考え方などと)の対比から見える両者の情報伝達媒体としての共通性の考察。ゲノム解読からわかる全生命の共通性と全個体の特殊性のお話。無生物から生物を作る挑戦のお話。遺伝子発現パターンをコントロールしているエピジェネティクスの重要性のお話、などなど。先生のお話を聞いていると、現在の生物学界の最先端では革命的な変化が起きようとしていることが良くわかりました。クローン、細胞の初期化、不死の細胞。SF小説に出てきそうな空想話が現実の話になりかけている、その臨場感と躍動感がお話を聞いていた学生側にも伝わり、会場は熱気に包まれました。先生が新たなイデオロギーの構築を科学者の立場からなさろうとしていることは先見的な素晴らしい試みだと感じました。それは現在の生命科学が科学者の好奇心によって突き動かされ、社会自身の変化を許容するスピードを超え暴走しているようにも思えるからです。新たな社会的、文化的、宗教的な火種を生みかねない危険性を内在している。iPS細胞は多くの可能性を秘めた正に夢の技術ですが、危険性も内在した諸刃の剣になるかもしれない。そのことを一番よく理解し、予想されうる混乱を回避できるのは他ならぬ生命科学者であり、自分たちはその責務を負っている。西川先生のお話からはそういった意思が感じられたように思います。今後のご活躍に注目です。
平田
勉強会の感想はこちら≫
■第四回<和田秀樹先生>

和田秀樹先生は様々な顔をお持ちで、一言でご専門が何かと断定することは難しいのですが、老人専門の精神科医、文筆家、大学教授、映画監督などのカテゴリーに属されるかと思います。メディアによく出られる方ですし、一般向けの著作も膨大にあります。肩書きやお仕事の範囲が多岐にわたるため、ともするとこの方の本質が見えにくいかもしれませんが、リアルな和田先生は大変熱い方で、日本社会に対する非常に大きな問題意識と強い正義感をお持ちの方です。その生き方は非常に独創的であり破天荒そのものですが、主張されることの筋が一本ピンと通った清清しさをお持ちです。非常におだやかなお人柄でしたが、学生とのディスカッションは白熱し、正に生き方から学ぶという言葉がぴったりの勉強会になりました。
私が一番感服したのは先生の目標が子供のころから映画監督になることで、その夢を諦めず、最近念願かなってモナコ国際映画祭で最優秀作品賞を受賞されたというお話です。和田先生が高校生のころには松竹に入り助監督、監督と進むキャリアパスがほぼ消滅していたため、映画監督への道が絶望的だったようです。そこでせめて自費で映画を取れるだけのお金を稼がねばと考え、国家資格が取得できる医学部に進まれたそうです。18歳でここまで考えて決断をされたのですから、並みの高校生ではなかったことはよくわかります。学生時代は自分の映画のヒロインを探すために女子大生用ファッション雑誌のライターをやって人材発掘を行ったり、興味がないのにアイドル研究会を立ち上げイベントを
企画したりと、行動原則が全て「映画のため」だったという筋の通し方が素敵です。やろうと決めたことは何が何でもやる意志の強さ、そして目的のためなら何でもいとわずやる前向きな姿勢。人生を全力でポジティブに生きるとこうなるのかと大いに感動しました。
先生のお言葉で印象的だったものに、『知的謙虚さ』、『知的好奇心』、そして『知的体力』が大切だというメッセージがあります。一つ目の『知的謙虚さ』とは、偉くなるほど人にものが聞きやすくなる、頭を下げやすくなるという趣旨です。これは前向きな和田先生ならではのご意見ですが肝に銘じておいてよい言葉かもしれません。二つ目の『知的好奇心』とは、問題解決能力よりも問題発見能力が大切という意味です。三つ目の『知的体力』とは人の気付いていない面白いことを発見したときに、それを真っ先にやりぬくだけの知的胆力を鍛えろという意だと解釈しました。人とは違う生き方をすることは大変だが、しかしだからこそ得られる自由もたくさんある。自由を得るため努力は惜しむな。コツは伝授した。そういった感じでしょうか。先生に負けず、多くの飯の種が持てるよう、ハングリーに生きて行きたいものです。
平田
勉強会の感想はこちら≫
■第五回<團紀彦先生>

團紀彦先生には昨年度に引き続き、今年度も講師をしていただきました。ご専門は建築で、最近のお仕事ですと愛地球博(2005)のマスタープランの作成、台湾の国際空港第一ターミナルのリフォーム計画、日本橋再開発プランのオーガナイザー等があります。国内外で広く活躍される日本建築界の第一人者のお一人といっても過言ではありません。先生のお人柄は温厚この上なく、しかし内に秘めたその熱い思いは鋭い眼光となって溢れ出ていました。プライベートでは素潜りの名手で、年に何度も大物を求め八丈島沖で潜っておられるとか。精神的にも肉体的にも非常にタフな素敵な方です。
LIPの勉強会では建築と現代社会のありようについての独自の論考が、建築と宗教、建築と文化との対比を通じて展開されました。何かある物事について考えるとき、どのような枠組みの中で考えるかという枠組み設定は、その後に展開されるロジック以上に重要で一番個性の出る所だと思います。團先生は異質なものが互いに影響を及ぼし合いながら存在するとき、どのような共存形態が可能かと考える場合、次の三つの形態を出発点としてとらえる枠組みを提案されました。すなわち、『分離』、『同化』、そして『調停』の三形態です。『分離』は文字通り異質なものを壁で仕切って分離してしまうこと、『同化』は片方がもう片方に同化することで摩擦を回避する共存形態です。それに対し、『調停』とは異質なもの同士が第三者の存在によって均衡し、異質ながらも調和が生まれる、そういった共存形態です。先生はこの三つの考え方をシンボリックに以下のように表現されました(左から『調停』、『同化』、『分離』)。
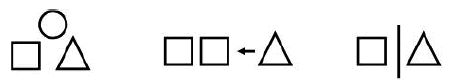
團先生曰く、『同化』と『分離』はキリスト教、ユダヤ教的な文化であり、西洋近代建築にもこの文化が強く反映されているということです。一神教的な思想背景があることは言うまでもありません。イスラム建築においても同様の傾向が見られるといいます。これに対し日本などのアジア諸国では多神教を基礎とした文化が根付いており、文化的に『同化』や『分離』よりも『調停』の方が自然であると指摘されました。
團先生の問題意識は、西洋で生まれた近代建築を文化の異なる日本でどう在来の文化と『調停』するかにあるといいます。戦後急速に近代西洋建築が輸入された日本では、適切な『調停』が模索される間もなく、ビル群や近代的な街並がどんどん形成されていったため、カオス的な状態になってしまいました。アモルファスのようにぐちゃぐちゃで無秩序な、典型的な日本の町並みの完成です。『同化』や『分離』ではなく、またアモルファスでもない、日本独自の秩序のとれた町並みをつくれないか。その解決策が『調停』だと團先生はおっしゃいました。和を尊ぶ日本ならではの『調停』のありかたとして、例えばまずは建物の道路に面した側面だけでも基調をそろえることはできないかと、実際のお仕事で建築家間の連携を深め、都市計画に統一性をもたせようと努力されているようです。建築のように後世にその影響が大きく残るお仕事は、その社会的責任も重大なのだと感じました。こと無かれ主義的な日本社会にあって、團先生のような問題提起は疎ましく思われること間違いありません。しかし100年、200年先のことまで考え、本当に必要なことはやり通そうとなさるお姿は尊敬に値します。スケールの大きな立派な方にお会いでき、LIPに参加してよかったと感じた回でした。
平田
勉強会の感想はこちら≫
■第六回<遠藤守信先生>

遠藤守信先生はカーボンナノチューブの研究において世界的な業績を誇る研究者であり、同時に大学発ベンチャーMEFS株式会社のCTOを勤められています。大変親しみやすい方で、技術のことを語るときに目を輝かせていらっしゃったのが印象的でした。講演はカーボンナノチューブとナノテクノロジーの話題を中心に、今後の社会のあり方や学生へのメッセージを語ってもらいました。
まず、ナノテクノロジーについて、人類の材料や物質観を変える革命的な技術であることに驚かされました。またナノテクの中でも特に期待を集めるカーボンナノチューブについて、遠藤先生が確立した生産技術によって、今現在、リチウムイオン電池の性能が飛躍的に向上しているという興味深いお話を聞くことができました。お話の中で、遠藤先生は、「日本は今後、イノベーション主導の技術大国へと脱皮しなければならない」と強調していました。中国をはじめとする新興国との生産技術競争は今後さらに激化するだろうこと、そして新しい技術を生み出すイノベーションを原動力としなければ本当に危機的な状況になるということを、実際に技術を生み出し、世に送り出している立場から熱い言葉で語っていただきました。思えば、今の日本はこれまでのやり方をいかに守るか、という空気がはびこっているように感じられます。遠藤先生のいうように新しい技術や仕組みを生み出す機運が、特に我々若い人間に求められているのだなと感じました。
また、遠藤先生が現在力を入れているカーボンナノチューブの安全性評価への取り組みについてもご紹介していただきました。技術倫理が大きな問題になる現在において、研究の第一人者であるからこそ積極的に安全性評価に携わるという姿勢に感動する内容でした。また、最近の「少しでも危険性のあるものは、問答無用で排除する」というやり方に対して、21世紀はリスクを定量的に管理できる社会になるべきだ、という主張に、大きく共感できました。今の社会が持つ危険やスキャンダルに対する脊髄反射的な軽薄さも、定量的に評価する枠組みを作ることで改善していけるかもしれないという希望を持つことができました。さらに遠藤先生ご自身の研究人生についても話が及びました。留学先で、年末に帰国もせず、研究室に防犯用のバリケードを作ってまで、ひたすらに実験を繰り返されたこと、やすりにまつわる思わぬ偶然からカーボンナノチューブの大量生産へと道を切り開かれたことなど、印象的なエピソードに会場が盛り上がりました。質疑の時間では遠藤先生から学生に向かって、広い視野を持つことも大事だが、まずは一つのことを突き進め、そこから幅を広げてほしいというメッセージをいただきました。遠藤先生のように一つの道を究め、さらに広い視点を持てるようになりたいと心から思える講演でした。
古川

勉強会の感想はこちら≫
■ご挨拶
2008年度のLIPでは高い見識と志をお持ちの日本を代表する五名の方々をお招きし、講義、並びに学生とのディスカッションに参加していただきました。2007年度から始まったLIP企画。その基本理念は秀でた能力と高い志をもった学生に対し、実際にすばらしい信念と優れた能力を併せ持ち社会の第一線でご活躍されている方々と議論する機会を設けることで、先輩方の生き方、職業観等に触れてもらい、自身のキャリアに対する具体的なイメージを描くきっかけを作って欲しい。というものです。また、専門分野を超えた知に対する渇望、思考することの楽しさ、大切さを一人でも多くの学生に再認識してもらいたい。このような思いからLIPは始まったと考えております。
今回来ていただいた講師の先生方は専門も所属も皆異なる、多彩な顔ぶれとなりました。全ての先生方に共通している点は、皆一つの道を極め、それに飽き足らず積極的に日本社会へ、あるいは人類全体へご自身の得たものを還元しようとされている点です。ここではそんな先生方との講義・ディスカッションの様子をReviewとしてまとめました。残念ながら実際の講義での熱い議論の全てをここに記すことはできませんし、また私にその能力もございませんが、可能な限り講義の様子が伝わるよう努力しました。私個人の視点を通しての捉え方なので、多分に偏見が入っておりますがその点はご容赦ください。
最後になりましたが、お忙しい中、我々学生のために遠路はるばる東京までお越しくださりました先生方に、この場を借りて改めて御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
LIP2008運営平田倫啓
|